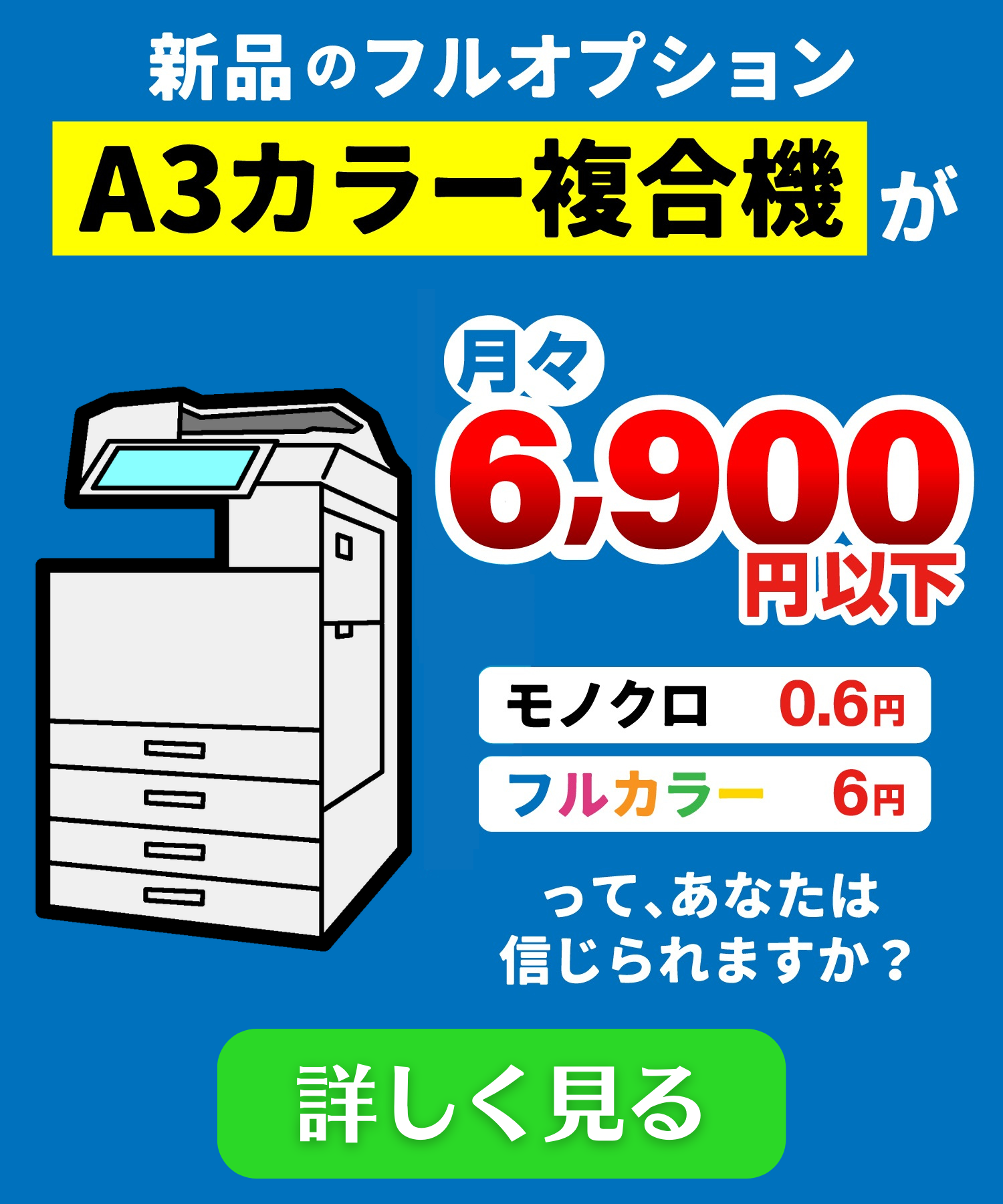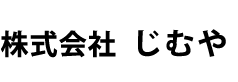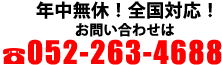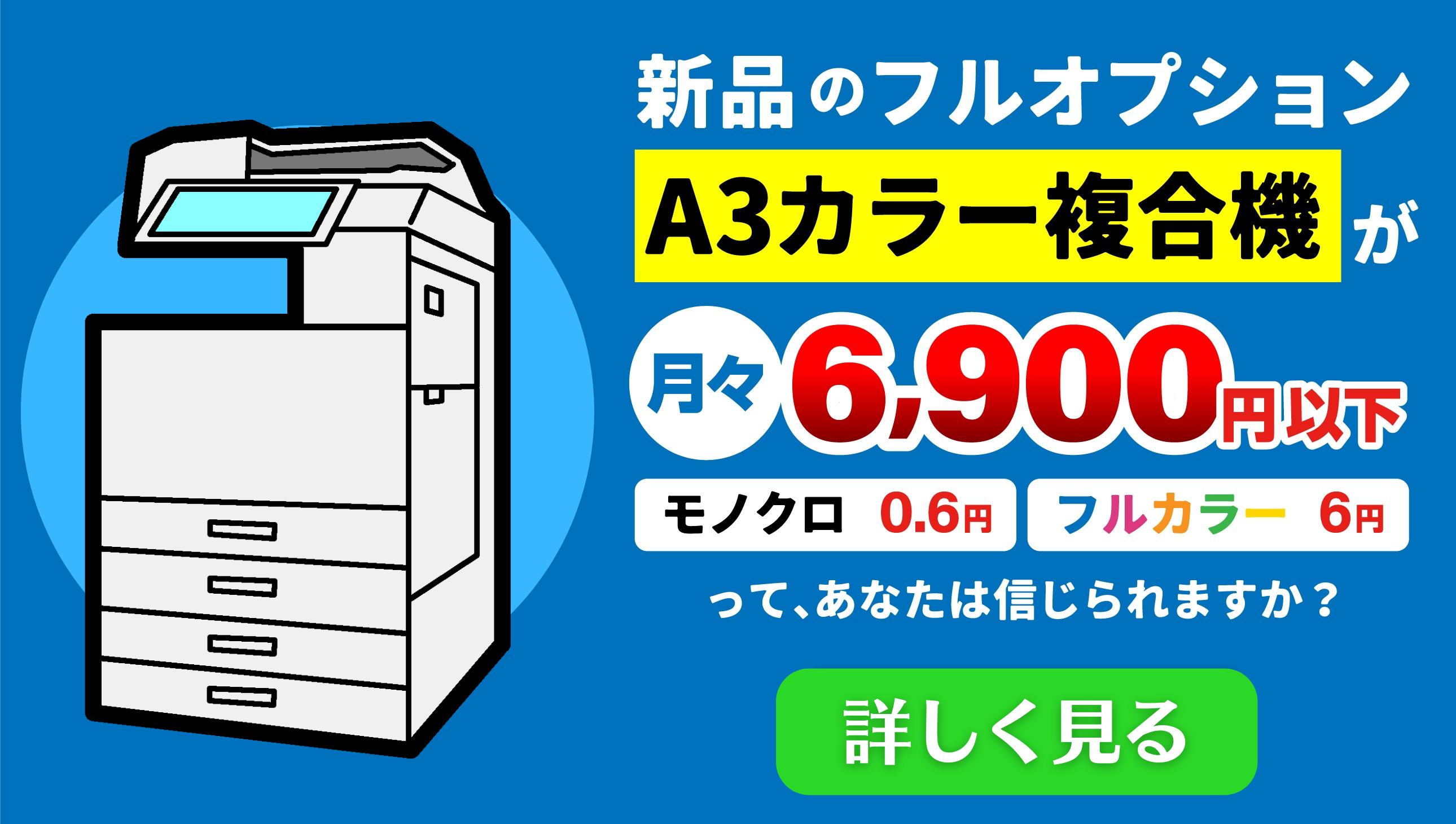複合機の法定耐用年数(減価償却期間)は何年?国税庁のサイトを調べ方も解説!
業務用フルオプションA3カラー複合機を月額6,900円でリース・販売している株式会社じむやの堀田です。
複合機は減価償却資産として税法上、10万円未満のときであれば消耗品費、10万円以上のときは備品や工具器具備品が一般的です。
そして、国税庁による耐用年数表では「複写機、通信機器」などの機器類は5年と定められています。
今回は、複合機の法定耐用年数について解説していきます。
ぜひ、最後までご覧ください。
目次
複合機における法定耐用年数とは?

法定対用年数とは、国が定めた使用期間のことで、その製品の本来の効果が維持できる年数でもあります。
企業が個々各々の製品で耐用年数を決めるのは不確定要素が強く、決算時の会計上でバラつきが出てしまうため、製品毎にカテゴリ分けをして法定耐用年数が定められています。
減価償却資産の「耐用年数」とは、通常の維持補修を加える場合にその減価償却資産の本来の用途用法により通常予定される効果をあげることができる年数、すなわち通常の効用持続年数のことをいい、その年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15号)により定められています
引用元:償却資産の評価に用いる耐用年数
国税庁の見解と併せて、さらに深堀りしていきましょう。
『国税庁の主な減価償却資産の耐用年数表』
国税庁が定める耐用年数表において、複合機(コピー機・プリンター含む)は「事務機器、通信機器」>「その他の事務機器」で分類されており、法定耐用年数は原則5年と定められています。
国税庁が定める複合機の耐用年数5年は、税務処理上の標準値として企業の会計担当者のなかでも定着しており、資産管理やリース・保守計画の設計にも影響しています。
実使用では5年以上の運用も可能ですが、保守費用や故障リスクの増加を考えると、5年を目安に買い替えや更新を検討するのが実務的にも合理的だといえます。
国税庁が発表している主な減価償却資産の耐用年数表は、こちらから確認できます。
『複合機における法定耐用年数に関する国税庁の見解』
国税庁が定める耐用年数表(別表)において定められている、複合機の法定耐用年数原則5年という分類は、製品が通常の業務使用に耐えうる期間として設定されており、税法上の減価償却期間として利用されます。
下記に、国税庁の見解を考察してみました。
5年という年数の妥当性
実際のところ、複合機はハイスペックであれば7年〜10年程度使用できるケースもあります。
ですが、法定耐用年数は減価償却によって資産価値を何年でゼロにするかという基準なので、現実の使用可能年数とは必ずしも一致しません。
あくまで、会計・税務処理上の目安です。
中古複合機の扱い
法定耐用年数を経過した中古複合機を導入した場合は、見積もられる使用可能期間に応じて、耐用年数を短縮して再計算することが可能です。
例を挙げるなら、耐用年数の20%を適用し1年とするケースなどです。
中古資産は減価償却を短期間で完了させられます。
リース契約や保守契約への影響
耐用年数5年という基準は、リース契約期間や保守契約期間(特にカウンター保守)と連動することが多く、5年使用してリプレースというサイクルが主流です。
これを超えて利用する場合、スポット保守への切り替えや、トラブル頻発のリスクが増えるため、実務上も5年を一区切りとするのが合理的です。
【関連記事】
新品の複合機の法定耐用年数は何年?
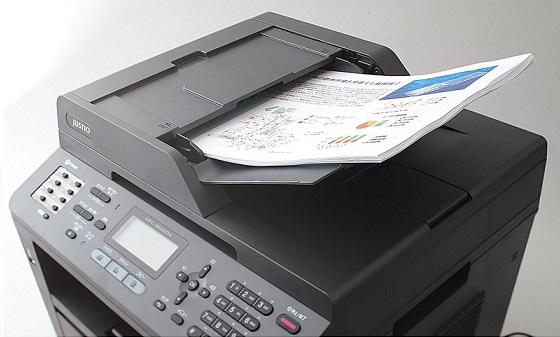
結論から書きます。複合機の法定耐用年数は5年となります。
国税庁の「耐用年数(器具・備品)(その1)」というページの「事務機器、通信機器」「複写機、計算機(電子計算機を除く。)、金銭登録機、タイムレコーダーその他これらに類するもの」で5年となっております。
法定耐用年数は昭和40年3月31日に耐用年数省令されました。
複合機は、このとき(昭和40年)の耐久性能が基準となって5年という数字になっております。
平成20年に一度改正されてはいますが、そのときに複合機の対応年数の見直しはされておりません。
中古の複合機の法定耐用年数は何年?
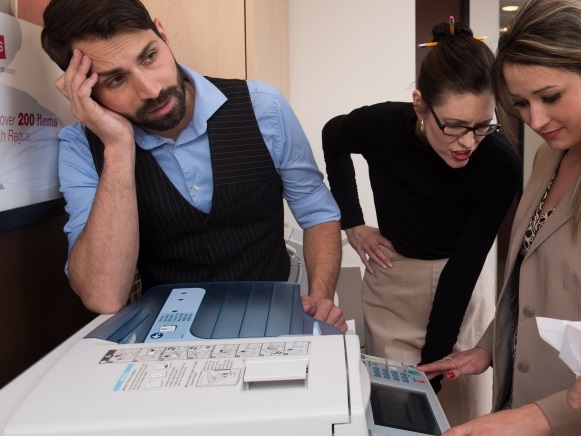
実は中古にも法定耐用年数というのが存在し、それを通称「使用可能期間」と言います。
ただ、中古には2パターンの考え方がありますので、計算式も含めてご紹介します。
中古資産を取得して事業の用に供した場合には、その資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができます。
引用元:中古資産の耐用年数
『製造年月日から5年以上経過した中古複合機の使用可能期間は?』
この場合の国税庁の定義では「その法定耐用年数の20%に相当する年数」を中古資産の使用可能期間と定めています。
すでに法定耐用年数が過ぎているので、複合機の法定耐用年数5年×20%に相当する「1年」が使用可能期間とされます。
『製造年月日から3年経過した中古複合機の使用可能期間は?』
この場合の国税庁の定義では「その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%に相当する年数を加えた年数」を中古資産の使用可能期間と定めています。
かなり、ややこしい文章なので、分かりやすく計算してみます。
①法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数
5年 - 3年 = 2年
②経過年数3年の20%に相当する年数
3年 × 20% = 0.6年(7ヶ月と2日)
③耐用年数(使用可能年数)
2年 + 7ヶ月と2日 = 2年7ヶ月2日
複合機の法定耐用年数=減価償却期間?

この法定耐用年数は、製品の法律の様な役割をしていますが、実は「法定耐用年数=減価償却期間」でもあるのです。
なので、複合機を現金購入した場合、5年間での償却が可能となり節税の効果も期待が出来ます。
ただ、「複合機を現金購入しても全額経費?【少額減価償却資産の特例とは?】」に記載もしておりますが、一括ですべて経費にできた方がよいときもあります。
個人事業主は必ず減価償却をしないといけないという事もありますので、上記の制度を使い利益が出すぎた分経費として使いたい場合におすすめです。
弊社では少額減価償却資産の特例の対応も行っております。
【関連記事】
減価償却の種類は?複合機導入後の注意点まで解説!

減価償却には「定額法」「定率法」の2種類の償却方法がありますので、それぞれの計算方法をご紹介したいと思います。
複合機を購入したとして、分かりやく解説していきます。
この後、数字として出てきますが、複合機を使い続けている限り減価償却は0円にしていけません。
普通の会社では1円を残すのですが、これは備忘価額と言い、無くなった物とある物を区別する為にあります。
前提として複合機を100万円で購入、法定耐用年数は5年とします。
『定額法の計算方法』
まず定額法の計算式は上記の様になります。
前提条件の複合機の購入代金を100万円、定耐用年数は5年として当てはめてみます。
1,000,000円 × 0.2(1÷5年) = 200,000円
これが1年間の減価償却費となります。
なので、1年で20万円×5年で丁度償却ができるということです。
| 1年目 | 1,000,000円 × 0.2(1÷5年) = 200,000円 |
| 2年目 | 1,000,000円 × 0.2(1÷5年) = 200,000円 |
| 3年目 | 1,000,000円 × 0.2(1÷5年) = 200,000円 |
| 4年目 | 1,000,000円 × 0.2(1÷5年) = 200,000円 |
| 5年目 | 1,000,000円 × 0.2(1÷5年) = 199,999円 |
しかし、複合機を定額法で減価償却する際には注意すべき内容もあります。
- 毎年同額を償却するため、年度ごとの節税効果が限定的
- 途中で売却・廃棄する場合は残存価額に注意が必要
- 備忘価額(1円)を残しておく必要がある
定額法では毎年均等に償却されるため、大きな初期費用を一気に経費にできません。
資金繰りへの影響が読みやすい反面、節税インパクトは分散されます。
5年以内に複合機を手放す場合、帳簿上の残存価額が残っているとその処理に注意が必要です。
売却益や損失が発生する可能性もあります。
それに、定額法で5年間償却しても資産台帳上では1円を残す備忘価額の処理をしなければなりません。
これを忘れると、会計上の整合性がとれなくなります。
『定率法の計算方法』
※その年が償却保証額(保証率)以下になった場合は定額法に変更
定率法の計算式は上記の様になります。
定率法償却率については定額法償却率の2倍となっていますが、小数点の部分で若干ズレがでますので、「減価償却資産の償却率表」を見てください。
計算の肝として、減価償却資産の償却率表の5年の場合の保証率「0.10800」の額を下回ったら、残りの年数分を定額法で割ります。
ここの部分が割とややこしいので「減価償却の計算サイト」で計算すると早いです。
前提条件の複合機の購入代金を100万円、定耐用年数は5年として当てはめてみます。
| 年数 | 未償却残高 | 定率法償却率 | 償却額 |
| 1年目 | 1,000,000円 | 0.4 | 400,000円(残600,000円) |
| 2年目 | 600,000円 | 0.4 | 240,000円(残360,000円) |
| 3年目 | 360,000円 | 0.4 | 144,000円(残216,000円) |
| 4年目(×) | 216,000円 | ||
| 4年目(〇) | 216,000円 | 0.5 | 108,000円(残108,000円) |
| 5年目 | 216,000円 | 0.5 | 107,999円(残1円) |
減価償却の定率法で複合機を導入した際の注意点を下記にまとめました。
- 初年度の償却費が大きく、年の経過とともに減少する
- 償却保証額を下回ると定額法に切り替える必要がある
- 償却計算がやや複雑で専門的な知識が必要
定率法は初年度に多く償却できるため節税効果は高いですが、年々償却額が減っていくため、数年後の経費が少なくなる点に注意が必要です。
一定の年数以降、定率法の償却額が保証額を下回ると強制的に定額法へ切り替わります。
このルールを把握していないと、誤った償却処理をする恐れがあるため注意しなければなりません。
定率法は毎年の残存簿価に基づいて計算するため、計算ミスが起きやすく、税務署対応も含めて正確な処理が求められます。
税理士に相談することをおすすめします。
リース期間は法定耐用年数を基準として期間が定められている!

今まで書いた事は全て現金購入した場合になりますが、リースの場合も法定耐用年数を基準として複合機のリース期間が定められています。
複合機は3年~7年の間でリースが組めます。
昔は5年のリースが一般的でしたが、最近では6年リースで契約するのが多くなってきております。
【関連記事】
『最短のリース期間の計算の仕方』
法定耐用年数が10年以上の製品【法定耐用年数 × 60% =最短のリース期間】
上記が最短のリース期間の求め方となります。
複合機の場合、法定耐用年数が5年なので70%になります。
これを当てはめてみると5年 × 70% = 3年(正確には3.5年)となるのです。
『最長のリース期間の計算の仕方』
上記が最長のリース期間の求め方となります。
これを当てはめてみると5年 × 120% = 6年となるのです。
複合機の7年リースはよいのか?

先ほどの複合機のリース期間で3年~6年までと書きましたが、実は「ジャックスリース」「オリコリース」「アプラスリース」では、7年リースというのが組める様になってきております。
最初の方で、この法定耐用年数が決められたのが昭和40年と書きましたが、昔から比べると複合機の基本性能自体が恐ろしく向上しているので、正直5年という耐用年数は現在では全く当てはまらないのです。
その為、後発のリース会社では法定耐用年数ではなく、部品の保有義務期間である7年に合わせてリース期間を決めています。
要するに7年間は保守が確実に対応ができ、耐久性も問題がないので7年リースが可能ということなんですね。
お客様のメリットとしては長ければ長い程、毎月の支払金額が下がりますので、その方がよいという方もいますが、7年リースで最初から提案してくる会社は、良い代理店とはいえないですね。
【関連記事】
今の複合機の法定耐用年数は寿命に関係がない?

今までご説明してきたとおり、法定耐用年数は複合機の寿命と違います。
法定耐用年数ぎりぎりまで使い続けるには、大切に取り扱っていかなければなりません。
複合機の寿命について、少し深堀りしていきましょう。
『複合機の寿命は5年』
ただ、複合機の寿命は?【期間5年 or 印刷枚数300万枚って本当?】というコラムでも書きましたが、使用してからの期間が5年 or 印刷枚数300万枚に到達したぐらいが寿命と紹介している会社が多いです。
業界歴10年以上の私から見ると5年という数字は、短すぎます。
法定耐用年数を基準として5年と書いている会社が多い印象ですが、普通に使用していて7年、酷使して5年というのが私が考える寿命かなと思います。
『複合機を長く使い続けるには』
複合機は高価なオフィス機器だからこそ、できるだけ長く使い続けたいと考える方もいるのではないでしょうか。
前述のとおり、国税庁が定める法定耐用年数では、業務用複合機の耐用年数は一般的に5年とされています。
これはあくまで税務上の目安であり、5年を過ぎたからといってすぐに買い替える必要はありません。
実際には、適切なメンテナンスと使用方法によって、耐用年数を超えても十分使い続けることができます。
定期的に清掃を行い、トナーや部品はできるだけ純正品を使うようにすると機械への負担が軽減され、トラブルも減らせます。
また、カウンター保守契約などを結んでおけば、万が一の故障時にも安心して対応できます。
法定耐用年数を迎えるころには、印刷の品質が落ちたり部品の供給が難しくなったりすることもあります。
そのような場合には、修理か買い替えかを判断するタイミングといえるでしょう。
耐用年数を超えて使う場合には、故障リスクやランニングコストとのバランスをみながら、慎重に検討することが大切です。
それに、複合機を長く使うには、日々の使い方や保守契約の見直しも必要です。
法定耐用年数を迎えたら補助・助成制度を活用して複合機を導入できる!

複合機の5年の法定耐用年数を迎えて新たに機器を導入する企業にとって、コスト面の負担は頭を抱えます。
そんなときこそ、補助金制度の利用がおすすめです。
『複合機購入で知っておきたい補助金・助成金の知識』
複合機は新品で100万円を超えることも多く、法定耐用年数を経過したタイミングでの買い替えでは、資金負担が重くのしかかります。
こうした費用負担を軽減する方法のひとつが行政の補助金制度。申請が通れば、一部費用が還付される可能性があり、企業としての信用度を高める効果もあります。
『補助金を申請するメリット』
最大のメリットは、初期費用の軽減です。
法定耐用年数を超えて使い続けた複合機の買い替えは避けられない出費ですが、補助金があれば、導入コストを抑えることができます。
申請には手間がかかるものの、審査に通れば大きな恩恵が得られます。
しかし、補助金の申請には、下記に注意してください。
- 受付期間
- 後払い
- 申請の手間
補助金制度には応募期間があり、毎年内容や対象が変わる場合もあるため注意が必要です。
補助金は導入後に受け取る仕組みが多く、初期投資は一時的に自己負担となるため注意しなければなりません。
それに書類の準備や申請作業には時間と労力がかかるため、スケジュールに余裕を持ちましょう。
『複合機導入におすすめの補助金・助成金制度』
法定耐用年数を迎えた複合機を入れ替えるなら、補助金や助成金の活用はおすすめです。
下記におすすめの補助制度、助成制度をまとめました。
- 中小企業経営強化税制
- 業務改善助成金
中小企業経営強化税制では、複合機などの設備を導入した際に即時償却、または取得価額の10%(または7%)の税額控除が受けられます。
法定耐用年数5年の資産でも、制度を活用すれば減価償却の効果を最大化できます。
また、業務改善助成金は、最低賃金の引き上げと生産性向上を条件に、複合機などの設備導入費用を助成してくれる制度です。
対象となる事業所は、規模100人以下かつ地域最低賃金との差が30円以内であることが条件です。
さいごに|法定耐用年数を意識して複合機を入れ替えよう!

今回は、複合機の法定耐用年数について解説してきました。
複合機は、日々のオフィス業務を支える大切な機器です。
だからこそ、法定耐用年数をひとつの目安にして、入れ替えのタイミングを見極めることが大切です。
国税庁が定める複合機の法定耐用年数は5年。これはあくまで税務上の指標ですが、実際には使用頻度やメンテナンス状況によって、性能の劣化や部品供給の問題が出てくるころでもあります。
印刷の質が落ちたり、突然の故障が増えてきた場合には、業務効率の低下や思わぬコスト増につながることもあるため注意しなければなりません。
長く使うことも大切ですが、無理に使い続けるよりも適切なタイミングで入れ替えることが、結果的によい選択となり得ることもあります。
法定耐用年数をきっかけに、今の業務に本当に合った複合機を再検討してみましょう。
無料の予約システム「タダリザーブ」
最新記事 by 堀田直義 (全て見る)
- 複合機の仕組み「OCR」とは?メリットやデメリットなど解説! - 2025年7月3日
- 複合機のデータ消去を行う方法とは?理由と対策について解説! - 2025年7月3日
- 複合機の高圧縮PDFとは?デメリットや解像度の違い等を解説! - 2025年7月2日
- 複合機のスポット保守とは?費用の相場やメリット・デメリットをご紹介! - 2025年7月1日
- 複合機の法定耐用年数(減価償却期間)は何年?国税庁のサイトを調べ方も解説! - 2025年7月1日